安富歩『合理的な神秘主義』『複雑さを生きる』:知の身体性・孤立性
第1回:「知」とは何か:知の身体性・個別性・孤立性・能動性・主体性

「知」は身体的である。
「学び」は身体的、故に個人的である。
ポラニーは次のように、知識と身体との関係を強調する。
我々の身体は我々が外界を知性的(intellectual)にあるいは実戦的(practical)に知ることすべてのための、究極の道具である。起きている間ずっと我々は、身体の外界のものとの接触への気づきを信頼し、それによってそのものに注意を向ける。我々自身の身体は、我々が通常は対象として経験しないこの世界の唯一のものであるが、我々は、身体から注意を向けている世界という形で、常に経験する。このように身体を知的(intelligent)に用いることで、我々はそれを、外界のものではなく、自分自身の身体だと感じるのである。
この意味で、我々がものを暗黙知の近似項(proximal term)として機能させるときには、それを、我々の身体に合体し(incorporate)、甚だしい場合にはそれを身体の中に包含し(include)、そうすることでわれわれはそのなかに住み込む(dwell)ようになる、ということができる。
この知識の身体性は、自然科学や数学の領域においても変わらない。(略)この身体の作動こそが知識にとって不可欠であり、それゆえ知識は常に「個人的」(personal)たらざるをえない。
それは、知識を保持する人の人格(personality)を包含しているとおいう意味で個人的であり、存在において原則的に孤独(solitary)である。しかしそこには、いかなる放縦の痕跡もない。
知識は、このように個人的・身体的であり、孤立的であるということが、何よりも重要なことである。(『合理的な神秘主義』p.173)
いくら説明をしても、学びは個人的、身体的だから、「仁」に至らない人がどうしたら「仁」にいたるの?
個人的・身体的・孤立的な学びであるために、自分独自のプロセスを辿らなくてはいけない。
ソクラテス・孔子・仏陀
違和感、気づき、エッジ、身体的メッセージ
暗黙知は身体性を帯びている。この世界でせわしなく頭だけが飛び出しそうになるほどの勢いで動き続けている。その速さの中で、暗黙知は沈黙してしまっているかもしれない。
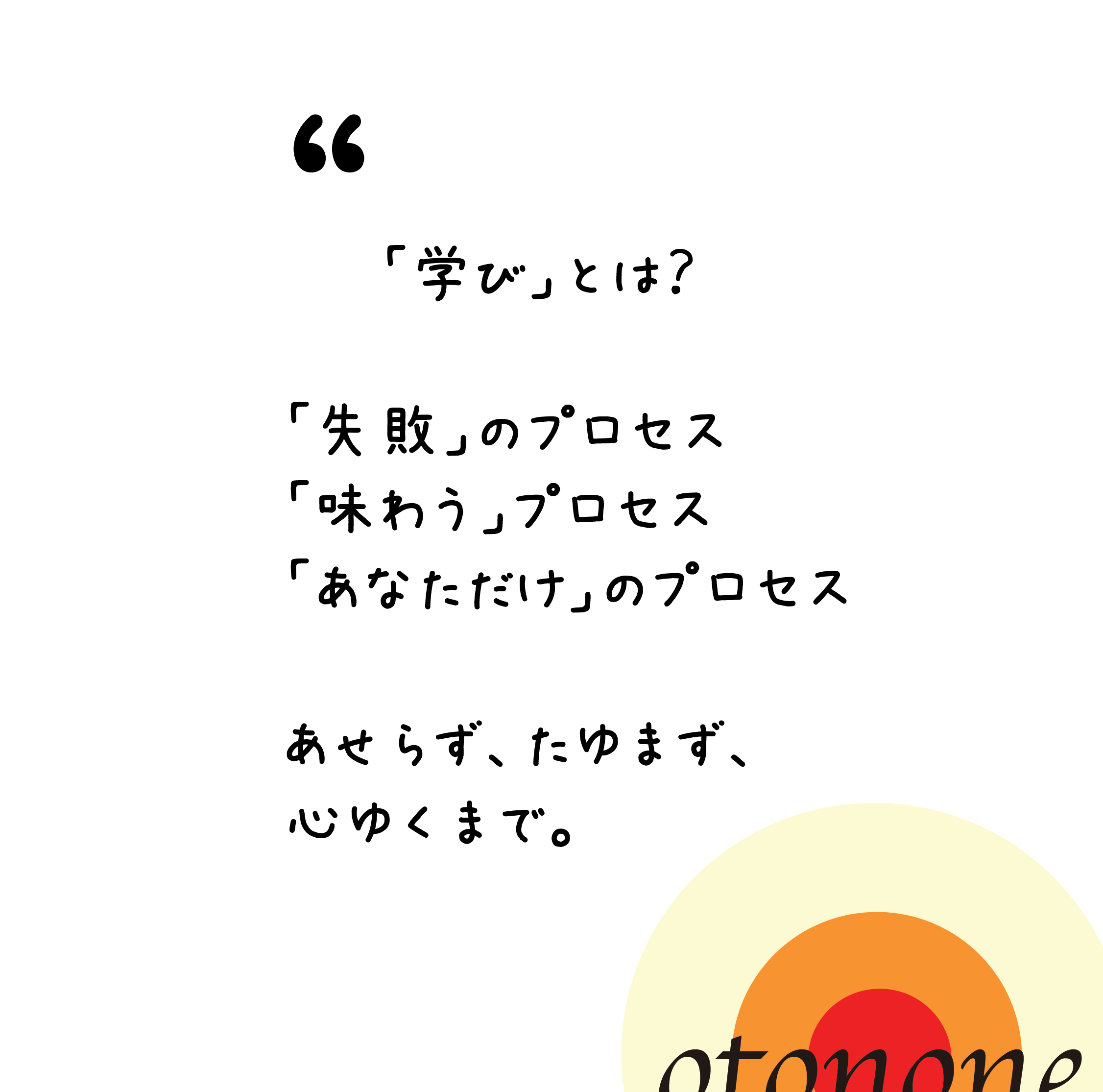
ポラニーの「暗黙知」
ポラニーは、戦前は科学者として活躍し、戦後に哲学者となった。最晩年に「暗黙の次元(tacit dimension)」という概念に到達した。ポラニーは「知る」という問題を徹底的に考えた。彼が強く批判したのは、知るという個人的過程を、「客観的知識」の「客観的操作」に置き換えよう、という迷信である。つまり、人間的主観的要素がある限り、知識は不完全であって、それをできるだけ排除すべきだ、という俗流の客観主義が、非科学的な妄想にすぎないということを、明らかにしたのである。パラニーは、たとえどんなに科学的な知識であっても、それは純粋に個人的な「知る」という過程の作動なしにはありえないことを、自らの科学者としての経験に基づいて示した。しかも、「知る」という過程を知ることは、原理的にできないので、これを「暗黙知(tacit knowing)」と名付けた。彼が強調したことは、知る、という過程を知ることができるのは、知っている本人だけであるが、知るという過程を知ろうとすると、知る過程そのものが止まってしまう、という問題である。知る過程そのものは、どう頑張っても、知ることのできない「暗黙の次元」に属している。(略)
私の最初の講義では、我々の暗黙知の力(our power of tacit knowing)を取り扱った。そこで示されたことは、暗黙知が住み込むこと(dwelling)によって理解(comprehension)を達成し、全ての知識(knowledge)がそういった理解の行為によって構成され、あるいはそれに根ざしている、ということであった。
このことから、「暗黙知」を「明示知」あるいは「形式知」といったものと対立させて理解することが、間違いであることが明らかとなる。全ての知識(knowledge)が暗黙知(tacit knowing)という人間の行為に根ざしている、ということを明らかにするのが、ポラニーの重要な論点なのである。(『合理的な神秘主義』安冨歩p.170)
私は人間の知識を再考するにあたって、我々は〈語りうることよりも多くのことを知りうる〉という事実から始めたい(I shall reconsider human knowledge by starting from the fact that we can know more than we can tell.)。
ここからポラニーは「語り得ない知識」があることを示す。(略)ものを指し示すという行為は、指し示される側が、相手の指し示していることの意味を受け止める努力をすることでのみ成り立つ、とポラニーは指摘する。いくらこちらが何かを指し示しても、相手が知らんぷりしていれば、どうしようもないのである。
確かに、外界の何かを意味する言葉の定義は、どんなものでも、究極的にはそういったモノの指し示しに依拠せざるをえない。モノを指し示してその名を言うというこの行為は「直示的定義(an ostensive definition)」と呼ばれているが、この哲学的表現は、言葉の意味を教えられるほうの、知的努力があってはじめて声うる断裂を、隠蔽している。我々のメッセージには、我亜wレノ語り得ないものが語り得ないままで残ってしまっており、それが受け取られるかどうかは、受け手側が我々の伝達しえなかったものを、自力で見出すかどうかにかかっている。
ポラニーが重視しているのは、このメッセージを受け取る側の努力である。そしてこの努力そのものは、「これこれこういうふうに努力しています」と語りうるものではない。これが暗黙の次元で作動する「知る」という過程、すなわち暗黙知(tacit knowing)なのである。(『経済学の船出』安冨歩 p.96)
暗黙知=明示的知識以前の情報を、わたしたちは知っている。
ポラニーは「明示的知識explicit knowledge」だけが知識を成り立たせているのではなく、その背後に作動する「暗黙に知ることtacit knowing」の重要性を繰り返し指摘した。先ほどの鍼灸師の例で言えば、注意を向けている患部の状態についてのイメージが「明治的知識」であり、手に伝わる鍼の動きから幹部の状態を生成する働きが「暗黙に知ること」である。(『複雑さを生きる』安冨歩 p.32)
差異(ちがい)の情報についてのベイトソンの議論が示すように、精神は差異を受け渡すサイクルに宿る。サイクルのなかには人間の皮膚の内側で閉じているものもあれば、皮膚を跨いでいるものもある。鍼治療のサイクルでは、鍼治療の手から針を通じて他社の皮膚の下の組織へと至っている。これ以外にも針灸師と患者の間に五感を通じたさまざまのコミュニケーションのサイクルが広がっている。皮膚の内側で閉じるさまざまのサイクルもある。例えば、神経系のなかで展開される神経細胞の発火が織りなす複雑な回路がそれである。我々の身体を舞台として、皮膚を跨ぐサイクルと、皮膚の内側で閉じるサイクルが複雑に相互作用している。全てのサイクルは差異を変換し情報を生み出している。この情報の相互作用のなかから「意味」が生成する。この「意味」が「知識」であり、精製の過程が「暗黙に知ること」である。「意味」が精製する以前に、皮膚を跨ぐサイクルのなかでは差異の変換が起きており、情報が生じている。言い換えれば、明示的知識が形成されるより前に、われわれの身体をめぐるサイクルに宿る精神は、すでに情報を「知って」いるのである。(『複雑さを生きる』安冨歩 p.34)
例えば「これは、なんだろうか」というなぞめいた情報の中に私たちは住んでいる。何ものかがいる、あるにも関わらずそれに「気づき」はしないものの、身体は情報として、暗黙知としてそれをもっている場合もあるだろう。「違和感」として気づけるものもあれば、
方便論的個人主義
それゆえ、私は、新たなる個人主義を求めねばならないと考えています。それはデカルト的な「方法論的個人主義」ではなくて、親鸞的な「方便的個人主義」であると。言い換えれば、世の中で起きていることのすべては、自分自身が自分自身のなかにはたらく真理に到達するための方便であるというのが、親鸞の教えの中でも特に大事なポイントではないかと考えているのです親鸞は、ブッダに始まり、龍樹や天親、曇鸞、善導、法然らを通じて与えられた浄土真宗の教えは、自分一人のためのものであったと言い切ったわけです。それと同じように、一人一人の学者が、あるいは一人一人の人間が、自分が生きて行くために必要な、自分だけ学問、自分なりの知識の体系を構築する、そのために、それぞれの人が考えたことを融通しあって助け合うということを、これからの学問のあり方として考えるべきではないかというのが、私の考えです。その場合の真理というのは、私にとっての真理以外の何物でもない。だから他の人から、そんなものはあなただけの真理であって、私には真理ではないと言われても、それは「面々の御はからい」で、一人一人のために真理はあるのだということをいえばいいのだと思うのです。(『生きるための親鸞』安冨歩・本多雅人 p.153)
主体性のない「知」はない。
行為することで知る。なぞることで知る。知は能動的。
試しにちょっと目を閉じて、人差し指をあなたのきている服の袖口にそっと置いて動かさないようにしてほしい。何か感じるであろうか。何も感じないので絵はないだろうか。次に指を静かに動かして服の表面をさすってほしい。衣服の繊維の作り出す微妙な凹凸を感じることができるであろう。指先から中枢神経を回ってサイド指先へと戻るサイクルを起動させ、指先を動かすという行為を組み込んで初めて近くは生じる。この場合にも、人差し指の先の神経は繊維そのものを入力とすることはできない。繊維のつくりだすちがいという普遍な状況が、指を動かすことによって手触りの変化という出来事を生み出して近くと行為の織りなすサイクルに入り込む。この簡単な実験は、指先の神経から入った刺激が脳に到達して対象の像を形成するという受動的な描写が事実ではないことを示唆している。皮膚感覚ばかりではなく、資格についても同様である。ものをじっと見るときには眼球が止まっているように思えるが、実際には眼球を支える筋肉が細かく振動しており、これによってはじめてものを見ることができる。さきほど服の手触りを感じるのに、指先を動かして袖口をさする必要があったのと同じように、目玉も世界をさすっているのである。生き物にとって世界は、者それ自体で構成されているのではなく、ちがいの知らせによって構成されている。われわれはこのちがいの知らせを手がかりとし、行為することで世界を読み解き、情報を抽出して生きている。抽出という主体的なかかわりなしに知覚は生じない。(『複雑さを生きる』安冨歩 p.14)
たとえばネットサーフィンをしていたとしよう。「あれ?この記事・・・」とどうして私たちは思えるのか。「その情報をまさに求めていた」とまでは思わないが、「気になる」という心の状態がある。その状態に至るネットサーフィン=なぞりから学習は始まっていて、「気になる」ところから深みが生まれてくる、と思えば、youtube徘徊も、「学」の一部なのだろう、か。
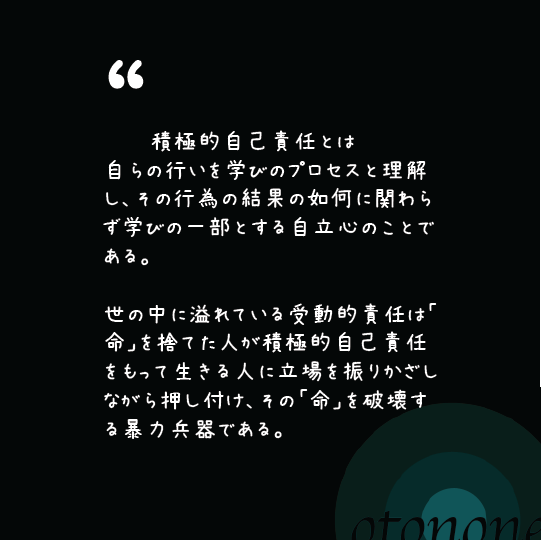
創発=新しいパターン
物理化学的世界の外から神の手によって生命が与えられたのではないとすると、医師の色の変化のルールカラうまいパターンが出現するような創発の過程、つまり生命の出現という過程を考えざるを得ない。同じことは生命が出現して以降の進化の過程にも見られる。無性生殖しかしなかった生命から有性生殖する生命が生まれる、単細胞生物から多細胞生物が出現する、中枢神経系を持たなかった生命から中枢神経系を持つ生物が出現する、さらにその果てには、自分の生命の意味を自分で考えようとするような人類の知性が出現する。このようにポラニーの創発という概念は、進化においてこれまでになぁつた機能が出現する過程を含む。
創発という過程の重要な副産物は「失敗」である。差異が差異を生み出す世界は創発の繰り返しによって階層的に構成されている。上位の階層の原理は下位の原理を破ることはないものの、下位の原理によっては規定されない。それゆえそこに新たな失敗の可能性を生み出す。上述のノイマンの自己増殖オートマトンの例では、石の白黒のうつりかわりは、必ずルールにしたがって行われる。しかし、初期の配置が少しでも間違っていれば、石のうつりかわりのなかでパターンが乱れ、自己増殖は実現されない。ルールに従いながら、それには規定されない自己増殖という機構の出現は自己増殖し損ねるという新たな失敗を伴っている。(『複雑さを生きる』安冨歩 p.42)
「創発」、人は「悪」をもっている?
生命の発生という最初の創発を原型として、進化の過程では次々と創発が繰り返され、新しい生命の携帯が、新しい原理とともに生み出されてきた。そのたびに新しい失敗の可能性も生み出されてきた。成長するという能力の創発は奇形という失敗を生む。新しい整理的機能の獲得は、その機能不全という失敗を生む。学習能力の獲得は、不適切な学習という失敗を生む。人間は道徳感情を持つがゆえに、邪悪になるという能力をも獲得してしまった。(『複雑さを生きる』安冨歩 p.43)
「学」に至る、「カオス的遍歴」と「暗黙の次元」(なめまわし、あじわい)
無秩序状態から秩序状態への遷移は徐々に起きるのではなく突然に起る。まるで落とし穴に落ちるように秩序状態がやってくる。これに対して秩序状態から無秩序状態への移行は要素間の佐賀倍々ゲームで増大して最後にバラバラになる。これに対して秩序状態から無秩序状態への移行は要素間の差がバイバイゲームで増大して最後にバラバラになる。倍々ゲームなのでゆっくりと移行するとは言えないが、突然に移行が起きる訳ではない。このような無秩序状態と、さまざまの秩序状態との繰り返しが、自律的に起きるダイナミクスのことを「カオス的遍歴」と呼ぶ。
これで一応準備が整ったので、知ることとカオスの関係について考えてみよう。これに直接関係のある重要な研究が、においを感じる器官についてなされている。においがするという近くは、におい分子が鼻の穴に飛び込んできて、粘膜表面の受容器にくっつくところから始まる。におい分子は三ー二〇の炭素分子を含む比較的小さな物質であり、非常にたくさん(数十万以上)の種類がある。これに対して人間は数千から一万種類の匂いを識別する。鼻腔内の嗅粘膜には匂いを管んじる嗅細胞があり、その数は人間では訳四〇〇〇万、犬ではやく一〇億に達する。嗅細胞の先端からは一〇ー三〇本の線毛が生えており、そこににおいに対する受容器がある。この受容体で重要な役割を果たしているタンパクがあるが、その種類は数百から一〇〇〇程度とされる。それぞれの嗅細胞にはひとつの種類の受容体のみが対応している。
におい分子の種類が数十万あり、受容体が数百種類しかないということは、におい分子の種類と受容体の種類とが一対一に対応していないことを示す。あるにおい分子に複数の種類の受容体が反応し、またある受容体には複数の種類の匂い分子に反応する。さらに、においの受容体の種類が数百で、においの識別が数千から一万ということは、これらもまた一対一には対応していない。つまり、ある匂い分子にある受容体が反応すると、においを感じる、というような単純な描像は成り立たないのである。現実の世界のにおいは、複数のにおい分子が金剛しており、その可能な組み合わせは無限にある。しかもにおい分子Aによって活性化する受容体のセットaと、におい分子Bに対応するセットbを考えた場合、ABをまぜあわせたものによって活性化する受容体のセットはa+bとはならず、新たなセットを生成する。人間お識別する「におい」はこの膨大な数の可能な組み合わせを、わずか数千種類にまとめていることになる。
このことは、嗅細胞の受容体ににおい分子が付いた段階では「何のにおいか」がわからないことを意味する。それどころか「何か匂いがする」ということすらわからない。受容体の活性化だけでは近くにも認識にも結びつかず、何かにおいがあるといった「知覚」はより高次のダイナミクスを必要とする。におい分子に反応することで受容体に発生した「ちがい」は軸索を通って鼻の奥にある嗅球という器官に集められる。フリーマンやケイによれば、嗅球の電気的活動は、におい刺激のない状態ではほぼ静止して弱いランダムな変動を示している。これに対して知っているにおいを嗅いだときには、周期解に似た動きをしたあとに、しばらく乱れた状態に推移し、それから別の周期会に似た動きを示し、また乱れ、ということをカオス的に繰り返すのである。つまり、
何もにおいがしない:ランダム
知っているにおいがある:周期解に近い弱いカオス
知らないにおいがある:カオス的遍歴
という関係が予想される。(略)フリーマンやケイによる一連の実験は、「知らないにおいがある」という自体がカオス的遍歴に対応し、「何もにおいがない」という事態がランダムな運動に対応することを明らかにしたことで、「知らないものを探求すること」が有り得ることを示したことになる。それは同時に、暗黙の次元の作動の実在を示したことにもなっている。(『複雑さを生きる』安冨歩 p.53)



コメント