安富歩『合理的な神秘主義』『生きるための親鸞』:「命」の神秘
第2回:「命」とは何かー神秘的な衝動
「命」は神秘である
スピノザの「コナトゥス」「衝動」
人間の生への努力たるコナトゥスが根本にあり、それが精神のみに関して認識される場合には「意志」と呼ばれる。それが精神と身体とに関して認識されると「衝動」と呼ばれる。言い換えればスピノザは意志を、衝動の精神的側面と見ているのである。そして衝動に人間の本質を見る。その衝動を意識しているときに、それを「欲望」と呼ぶ。コナトゥスはすなわち「衝動」であり、その身体的側面を無視すると「意志」に見え、それを無視しない場合は「欲望」となる。そういう「衝動」「意志」「欲望」の対象となるものを「善」と判断するのである。(『合理的な神秘主義』安冨歩 p.94)
「今、いのちがあなたを生きている」というのはまさにスピノザの言う、コナトゥスの流れに従って生きるということ、私が生きているのではなくて、私の中の作動、これが「私が生きている」ということなのだと思います。このコナトゥスの作動を自分の力で破壊したり止めたりするというのは、私たちにはできないし、本来、ありえないことだと思っています。ですから、私は自殺というのは殺人だと考えています。それは外部の力で自分自身を殺させるというのは、まさにコナトゥスに反することなのです。私は、「今、いのちがあなたを生きている」というのは、これを直接に表現したものだと感じています。(『生きるための親鸞』安冨歩・本多雅人 p.62)
エピクロスの「快」=身体のメッセージ
エピクロスは、生きることそのものを肯定し「身体の健康と心境の平静こそが祝福ある生の目的」だと考える。そして次のようにいう。
快が現に存しないために苦しんでいるときにこそ、われわれは快を必要とするのであり、〈苦しんでいないときには〉われわれはもはや快を必要としない…まさにこのゆえに、われわれは、快とは祝福ある生のはじめ〈動機〉であり終わり〈目的〉である、と言うのである。(略)
この「快」は「思慮」と結びついている。すなわち、
思慮は、思慮ぶかく美しく正しく生きることなしには快く生きることもできず、快く生きることなしには〈思慮深く美しく正しく生きることもできない〉、と教える。
という。このように生きる人物がすぐれた者である。(略)エピクロスの言う「快」は当然のことながら、肉体の教えるところである。それゆえエピクロスは肉体を肯定する。(略)この肉体の教える善を受け入れて快にしたがって生きることができないときに、我々は不正を為す。
けだし、自然な快が、われわれに不正を行わせるのではなくて、むしろ、むなしい臆見と結びついた欲求が、不正を行わせるのである。
(『合理的な神秘主義』安冨歩 p.51)
問:「自然な快」はどんなもの?「むなしい臆見と結びついた欲求」とはどんなもの?
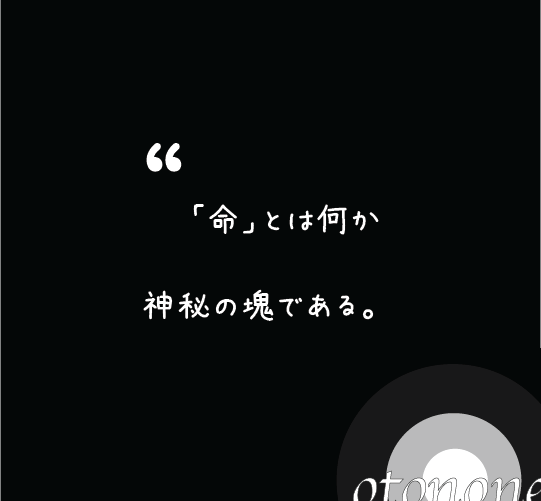
ヴィトゲンシュタインの「語りえぬもの」「世界の外」にあるもの
彼はその主著、『論理哲学論考』の最後を、
七 語りえぬものについては、沈黙せねばならない。
という命題でしめくくった。別の箇所でも、
六・四一 世界の意義は世界の外になければならない。…世界の中には価値は存在しない…価値の名に値する価値があるとすれば、それは、生起するものたち、かくあるものたちすべての外になければならない。
と述べている。ヴィトゲンシュタインは、語りうるものによってすべてを覆い尽くそうとする妄想が、世界の価値や意義を破壊していると考え、神秘を取り戻すことで人間を正常化しようとしていた。彼は次のようにも言っている。
六・五二 たとえ可能な科学の問いがすべて答えられたとしても、生の問題は依然としてまったく手つかずのまま残されるだろう。これが我々の直感である。
(略)ヴィトゲンシュタインは命題(四・〇〇三)で、
「哲学的事柄についてこれまで書いてきた命題や問いの大部分は、偽なのではなく無意味なのである」
と大胆に指摘した。というのも、哲学が扱ってきた問題の多くが「語りえぬもの」だったからである。(『合理的な神秘主義』安冨歩 p.162)
世界の外、というのは、「語りえぬもの」の世界、ポラニーの「暗黙知」が生まれる「暗黙の次元」のことであり、清沢の「如来」がおわしますところでもあり、スピノザの「生への努力(コナトゥス)ー衝動」が生まれるところであり、孟子の「怵惕惻隠之心」が生まれる場所であり、ラッセルの「内なる声」が発せられるところであり、李卓吾の「童心」がはたらくところでもある。「神秘」とも呼ばれる。
六・四四 神秘とは、世界がいかにあるかではなく、世界があるというそのことである。
六・五二二 だがもちろん言い表しえぬものは存在する。それは示される。それは神秘である。
(『合理的な神秘主義』安冨歩 p.166)
「学」に至る、「よろこび」
学習能力は、脅しや圧力によっては、決して作動しない。『論語』の冒頭の言葉。
「学んで時にこれに習う、またよろこばしからずや」
という言葉の示すようにそれは、悦びによって作動する力である。この回路を保持するためには、人は勇気を持たねばならないが、それは子供時代に脅かされず、全面的に受け入れられることによって初めて、可能になることなのである。我々が狂気の連鎖から抜け出し、正気の社会を構築するためには、私たちが子ども時代に何をされたのか、という決して知りたくはない真実に勇気を持って直面することである。それから我々の感覚を取り戻し、学習回路を作動させ、そうして初めて我々には、口先だけではなく、本当の意味で、子どもを守ることが可能となる。
子どもの魂を守ること。子どもから、子ども時代を奪わぬこと。
これが、我々の社会にとって、人類がこの危機の時代を生き延びるために、そして地球を破壊から守るために、何よりも大切なことなのである。これが多くの先人の智慧の教えるところだと、私は理解している。(『合理的な神秘主義』安冨歩 p.303)
ブッダの「縁起」ー「確実なもの」はない
正しく見、正しく知った諸々の賢者・ヴェーダの達人は、悪魔の繋縛に打ち勝って、もはや迷いの生存に戻ることがない。(『合理的な神秘主義』安冨歩 p.36)
このレベルでの自分自身との真実との出会いこそが、ブッダの示した智慧への道であり、人間の自由の根源である。それは、言葉の背後にある何かを「実体」だと思い込んでしまい、それに振り回されてしまう、という病からの離脱である。(略)我々の世界は非線形性に満ちており、そのような世界に直面しながら生きている。という事実の前では、何らかの「確実なもの」にしがみつく姿勢は、隷属への道以外の何者でもない。我々は、複雑さの中で動的に対応して生きていく能力を生れながらにして持っているのであって、我々の身体に込められている驚くべき創発的計算能力を信頼し、その感覚に従って、信頼しうる人を信頼し、信頼しえぬ人を信頼しないで、頼りになるネットワークを構築して生きていけば、それで十分なのである。(『合理的な神秘主義』安冨歩 p.299)
「学び」=「気づき」
安冨 あのとき、同席されていた宗会議員の方のご体験なのですが、統合失調症の息子さんがおられたと。それで、本人も家族も長いこと苦しんでこられたそうなのです。その方は、わが子ではあるが過程をメチャクチャにしてしまった息子のことを、嫌っていたそうです。ところが、あるとき、その息子さんにこう言って避難された。「お父さんはこれまで僕のことを褒めてくれたことがなかった」と。そのとき、ハッとされたそうです。そう言えば、これまで自分は息子のことを一度も褒めたことがなかったと。そのとき、初めてその議員さんは、「すまんかった、お父さんは一度もお前のことを褒めたことがなかった」と、心の底から息子さんに謝られた。そうしたら、息子さんはぼろぼろと涙を流して泣かれたそうです。息子を統合失調症にした原因が自分にあったことに、そのときはじめて気づかれた。「おまえはそんな姿になってまで、私が傲慢な親父であったことを教えてくれたのか」と。「私はそれまで、勉強しないで学歴が低く、卑しい仕事をしている人などは、くだらない人間だと思って見下すような、そういう考えをしていました。息子にそんな考えが間違っていることに気づかされました」とおっしゃっていました。こおういった体験の受け止め方は、まさに親鸞の方便論的個人主義だと思います。(『生きるための親鸞』安冨歩・本多雅人 p.107)
ラッセルの「内なる声」
もしラッセルがはじめ確実な知識に到達する希望に燃えていたのでなければ、彼の哲学的方法は決して形成されなかっであろう、と私は信ずる。確実制が到達し得ないものであることを初めから心得ていたのならば、彼は哲学を捨てて経済学か歴史学かに没頭したであろう。
(略)ラッセつの「負け戦」が何との戦いであったかを知る上で、興味ふかい記述が『私の哲学の発展』のなかにある。彼が十六歳のときに書いた日記の一部である。
私がそれによって自分の行動を導き、かつそれにはずれることを罪と考えるところの、生活の規則は、幸福の強度と幸福に預かる人間の数の両方を考慮して最も大きな幸福を生み出すに違いないと思われるような仕方で行動すること、である。私の父母はこれを実行不可能な生活規則だと考えており、人は最大の幸福を生み出すものを決して知り得ないのだから、内なる声(the inner voice)に従う方がはるかによいといつも言っているのを、私は知っている。…私の信ずるところによれば、良心(conscience)は進化と教育との共同の産物であるにすぎないのだから、理性(reason)を捨てて両親に従うことは、馬鹿げている。
私には、ここからラッセルの無謀な戦いが始まっており、「理性」に絶対の信頼を置いたラッセルが全知全能を振り絞って戦いながら、「内なる声」を信ずる父母に、一歩一歩追い詰められて行った、ということではないかと考えている。内なる声は、単なる両親ではなく、よりふかい計算に支えられた、洞察・直感・直観・予見の源であった、ということであろう。(『合理的な神秘主義』安冨歩 p.143)
孟子の「怵惕惻隠之心」=「暗黙知」
孟子は、人間社会の秩序の根源を、「怵惕惻隠之心」に求めたのである。これは人間が、ハッとして、思わず抱く心の動きのことである。これは明確に『論語』の学習思想の継承であり、また発展である。なぜなら、学習過程は、このような意識される前の身体反応に依拠して生じるからである。その身体反応が正しく作動し、それを認識することのできる状態が「仁」であり、そうなっているない状態が「不仁」である。孟子の思想は「性善説」と呼ばれることがあるが、それは必ずしも正しい表現ではない。というのも「怵惕惻隠之心」が「善」なのか「悪」なのかは、それ自体としては判定のしようがないからである。とはいえ、そのような生得的な身体反応に秩序の根源を見る、という意味で、「性が善」だというのである。(『合理的な神秘主義』安冨歩 p.47)
問:「怵惕惻隠之心」を守り、育てるためには?
清沢の「如来」=コントロールされぬもの、ただやってくるもの
「相対・有限」というのは「この私」、「絶対・無限」というのは「如来」のことだと考えれば良い。それゆえ精神主義というのは、この私と如来との合するところに生じる、実際上の問題、つまり、生きる、という場面での私自身の態度のことだ、というのである。どういう態度かというと、これは渋沢最晩年の「我は此の如く如来を信ず)我信念)」という論文に出てくる次の有名な文章は端的に示している。
人智は有限である、不完全であるといいながら、有限不完全なる人智を以て、完全なる標準や無限なる実在を研究せんとする迷妄を脱却し難いことである。私も以前には、心理の標準や善悪の標準がわからなくては、天地も崩れ、社会も治らぬ様に思うたことであるが、今は、心理の標準や善悪の氷筍が人智で定まる筈がないと決着して居りまする。
つまり、人智を以て得られそうな標準で判断するのではなく、そのような能力の完全な欠如を自覚し、その上で、如来を信じて「虚心平気に此世界に生死する」のが「精神主義」である。
清沢の挙げている具体例を見ることにしよう。彼が論じているのは、部屋にいるときに地震にあったらどうするか、と謂う問題である。地震だからといって、走り出したら災害に遭うこともあれば、逆に走りでなくて災害に遭うこともある。それのどちらが良いのかは、あまりにむずかしいので「吾人の知見し得る所にあらざるなり」と言わざるをえない。ならばどうするか。清沢は言う。
知見し得ざることに対して狂乱するは無用のことなり、吾人は、此無用のことに対しては、勤めて虚心平気の工夫を尽くし、面して、走出るべきか走りいずべからざるかの直接問題に対しては、一に無限大悲の指命に待ち、もし走り出んとするの念起らば、幕直に走進し、若し走り出んとするの念起らずは、泰然として安坐すべきなり。
つまるところ、虚心平気に「走り出たい」と思うなら、それは如来の指命なのだから、まっすぐに走りでるべきであり、「走り出たい」と思わないなら、泰然自若としてそこにじっとしていれば良い、といのである。これが「他力」という態度である。しかしこれだけでは済まない。なぜなら、「其他力の指命が判然たらざる場合」、つまり何らの念も起きず、気持ちがはっきりとしない、という場合があるからである。これについて清沢は次のようにいう。(略)もしどうしかいいか判然としない場合には、それもまた如来の「妙巧」なのであるから、これまた虚心平気に、「指命を待ちつつ満足」して、迷っておれば良い、というのである。このような解決は、「○○という情況で、Aという行為と、Bという行為とが可能である。さてどちらが倫理的に正しいか」というタイプの選択問題を、すべて無意味にする。このような考え方は、「標準を求めるものであり、清沢はそれは人智を超えた問だ、と考えていた。それゆえ、こういう問の設定そのものが無意味だ、というのである。此のような発想は、「決定論/非決定論」という二項対立を打ち破る、二項同体の思考法である。(『合理的な神秘主義』安冨歩 p.132)
問:ソクラテスのダイモーン、如来を「信じる」に至るプロセスは?
スピノザの「神」=「自然」=目的なき永遠・無限の実有
スピノザはこの世に存在するものすべて、つまり自然そのものが神である、という以外に、絶対無限の唯一鳴神はありえないとしたのである。スピノザのこの考え方は「神即自然」というように表現される。この世界そのものが神であり、神とはこの世界そのものである。神に「目的」はない。
我々が神あるいは自然とよぶあの永遠・無限の実有は、それが存在するのと同じ必然性をももって働きをなすのである。…神は、なんら目的のために存在するのではないように、また何ら目的のために働くものでもない。
このような神は全能であり、誰にも拘束されることなく、自らの本性に従って無目的に作動し続ける。その作動とは、自分自身を自分自身で生み出し続けることであり、何かの「ために」あるいは何かの「目的で」作動する、というようなことは考えられない。この意味で神は絶対的に自由である。なお「自由」とは次のように定義されている。
自己の本性の必然性のみによって存在し、自己自身のみによって行動に決定されるものは自由であると言われる。
このような神=自然は、この私自身と切り離されていない。それどころか、この私自身は、神=自然の働きの一部である。(『合理的な神秘主義』安冨歩 p.89)
問:自らの本性に従って無目的に作動し続けるなら、「悪」なんてものはないのだろうか?




コメント