安富歩『経済学の船出』『複雑さを生きる』『ドラッカーと論語』:コミュニケーション
第3回:「コミュニケーション」する「心」
コミュニケーションはリスクをともなう。
コミュニケーションでハラスメントのリスクを負う
ドラッカーによれば、コミュニケーションの基本原理は次の4つである。
1コミュニケーションは認知である。
2コミュニケーションは予期である。
3コミュニケーションは要求する。
4コミュニケーションと情報とは、異なった、というよりほとんど反対のものであるが、それでも相互に依存している。
第一の原理は、「聞く人のいない森で樹が倒れたら、音はするか」という有名な公案に表現されている。ドラッカーによれば、これは、禅僧、イスラムのスーフィー、ユダヤ教のラビなどによって古くから考えられてきた問いであるという。この公安に対する正しい答えは「音はしない」である。音波が生じても、それを聞くものがいなければ音はしない。弟は認知によって創造されるものであり、音を聞くということは、すでにコミュニケーションなのである。
この公安は、コミュニケーションは受け手がするものだ、ということを含意している。いわゆるコミュニケーター、すなわち送り手は、コミュニケーションをしていない。彼は叫んでいるだけである。誰かが彼の叫び声を聞いて認知してくれるまで、コミュニケーションは発生せず、そこにはノイズがあるだけである。(略)
受け手が主体であるがゆえに、受け手の受容可能な範囲が、コミュニケーションの実現可能範囲となる。この点は、プラトンの『パイドン』のなかでソクラテスによって表現されている、とドラッカーは指摘する。ソクラテスは、人に話しかける際には、受け手の経験に基づく言葉で話さねばならず、例えば大工に話しかけるには、大工の比喩を使わねばならない、という。つまり、コミュニケーションの主体である受け手の機体の範囲内でしか、コミュニケーションは成立しない、とドラッカーは考える。(略)
ここでは受け手の「制約」について二つのことが言われている。第一に、受け手には、身体的、文化的、感情的制約があり、その範囲を超えたメッセージは無視される、ということである。第二に、受け手が経験に基づいて感情を変えるという意味での学習過程を作動させていなければ、コミュニケーションは成立しない、ということである。この両者は矛盾しているわけではない。第一の場合は、受け取り可能範囲の問題であり、そこを超えたメッセージは「無視」される、ということである。第二の場合は、たとえ受け取り範囲にメッセージが入ったとしても、それによって受け手に「経験に基づいて感情を変える」という出来事が生じなければ、メッセージは何の変化も起こさず、それゆえ「何も新しいことはない」という形で処理されてしまうのである。これは「黙殺」と言うことができる。先ほどのキャッチャーの比喩でいえば、たとえキャッチャーの受け取り可能なボールが投げられても、キャッチャーに受け取る気がなければ、ボールは受けられない、ということである。(『経済学の船出』安冨歩 p.118)
」
メッセージの発し手は「叫ぶ」だけであって、それだけではコミュニケーションは生じない。誰かがそれを受け止めて、心を動かすことが決定的条件である。コミュニケーションが生じるには、受け手が、自らの経験に基づいて感情を変える、と言う学習の構えを開いておかねばならない。
以上に立脚するドラッカー経営額の根幹は次のようにまとめることができる。
(1)自分の行為の影響の全てを注意深く観察せよ、
(2)人の伝えようとしていることを聞け、
(3)自分のあり方を改めよ。
これは個人に対しても、組織全体に対しても当てはまる。(『経済学の船出』安冨歩 p.130)
「コミュニケーション」は賭けである。
「痛い!」といった後、相手は、、、
「わたくし」がそうやって大騒ぎした結果、「あなた」が私の足の小指をさすってくれれば「わたくし」はうれしい。「あなた」が爪切りを持ってきてくれたとしたら、それは何かおかしいから「わたsくし」は怪訝な顔をする。それがノコギリだったら絶対におかしいので、苦しい息の下から「なんでや!」と叫ぶ。そういったやりとりを繰り返して、互いに師匠のないところまで持っていくことができれば、通じているといえる。コミュニケーションとは「わたくし」と「あなた」が、互いにわかりあおうとして、相手の繰り出してくる行為を、相手の心を推測しながら読み解くという形でしか実現し得ないのであり、そうすることでこそ実現しうるものなのである。(略)こういった状況を前提にしてコミュニケーションを実現させるためには、相手が自分と同じような世界を持っている、とまずは信じ込み、なんらかの動きを示すという賭けにでなければならない。賭けである以上、それは危険を伴っている。たとえ身体的気概を被る事態にならなくとも、とんでもないまちがいをする可能性がいつでもある。この賭けを「うまく」やるための技芸とは、自分のでう相手についての「理論」を形成することである。この理論を駆使して他者の行為を解釈し、他者に対する行為を生成し、その繰り返しの中で異論を発展させていく。コミュニケーションが生成する連鎖の中で「わたくし」はさまざまの他者との間で場を形成し、人格を形成するが、この人格とはさまざまの他者についての「理論」と、それを駆使する技芸の相対であるということもできよう。(『複雑さを生きる』安冨歩 p.69)
コミュニケーションとはハラスメントの「リスクを負う」こと
自分は母親に愛されているというストーリーを守るために、母親に愛されていないという自分の感覚を捨てるのが、自分に対する裏切りの第一歩である。人間という生き物が、完全に「本来の自分」を展開させることなどありえない。たとえば自由奔放に、自分だけに通じる言語を喋るようになってしまうと、誰ともまともにコミュニケーションをとることができなくなってしまう。なんらかの規範を持たずに自己を形成することはできない。自己というある一貫したストーリーを保持するためには、多くの内的外的情報を無視し、封じ込めなければならず、実際、脳はそのような機構をもっているのである。
自己というものがそもそもこのような機構の上に成り立っている以上、「自分に対する裏切り」から人間が完全に逃れることはあり得ない。それゆえ、コミュニケーションはハラスメントの契機から完全に自由にはなりえない。必要なことはハラスメントを根絶しようとすることではない。それは不可能ごとであり、不可能なことを可能だと称することは、ハラスメントを生み出す契機となってしまう。われわれひとりひとりは幸福に生きるために、ハラスメントの魔物が自分の周囲の関係のなかに蔓延することを阻止せねばならない。それは自分の学習過程を鍛えることであり、他人の学習過程の作動を促すことである。自分の感覚を信じ、本来の自分を生かしている人とつながり、そうでない人には「そのようなことをするな」と断固たる姿勢を示すことである。これがハラスメントと戦う唯一の方法であり、人間が生きるために学ばねばならない最も重要なことである。(『複雑さを生きる』安冨歩 p.94)
問:学習過程を作動させるには、裏切りに気づくには?
ポラニーの「暗黙知」
私は人間の知識を再考するにあたって、我々は〈語りうることよりも多くのことを知りうる〉という事実から始めたい(I shall reconsider human knowledge by starting from the fact that we can know more than we can tell.)。
ここからポラニーは「語り得ない知識」があることを示す。(略)ものを指し示すという行為は、指し示される側が、相手の指し示していることの意味を受け止める努力をすることでのみ成り立つ、とポラニーは指摘する。いくらこちらが何かを指し示しても、相手が知らんぷりしていれば、どうしようもないのである。
確かに、外界の何かを意味する言葉の定義は、どんなものでも、究極的にはそういったモノの指し示しに依拠せざるをえない。モノを指し示してその名を言うというこの行為は「直示的定義(an ostensive definition)」と呼ばれているが、この哲学的表現は、言葉の意味を教えられるほうの、知的努力があってはじめて声うる断裂を、隠蔽している。我々のメッセージには、我々の語り得ないものが語り得ないままで残ってしまっており、それが受け取られるかどうかは、受け手側が我々の伝達しえなかったものを、自力で見出すかどうかにかかっている。
ポラニーが重視しているのは、このメッセージを受け取る側の努力である。そしてこの努力そのものは、「これこれこういうふうに努力しています」と語りうるものではない。これが暗黙の次元で作動する「知る」という過程、すなわち暗黙知(tacit knowing)なのである。(『経済学の船出』安冨歩 p.96)
主体性、それは人間性「暗黙の次元」
コンピューター内にある情報というものは、組織内へと処理されたデータにすぎず、それをいくら眺めたところで、組織が今必要とする情報は得られない。そこで、データに関連性と目的とを与え、意味を生成する「知ること」という人間の主体的な活動が必要となる。そして適切な目的を与え、それにふさわしい関連性を形成するには、この意味での「知る」という作動が不可欠である。(略)ドラッカーは知識というものが急速に陳腐化していく、としてそれを防ぐためには「継続学習」が必要だと述べている。(略)このような知識と学習の関係については、やはり孔子も同じようなスタンスをとる。『論語』にはこのような一節がある。
仁は、仁であることそれ自体が安定性の根拠である。知は、仁によって支えられている。
このことからわかるのは、データを情報に転換するには、たゆまぬ「学習」が必要不可欠であるということだ。データに「関連性と目的」を与える、という行為は、実はデータそのものとど効率にできることではない。事前に想定した関連性・目的にこだわっていると、有効な意味を生成することはできない。データとの対話のなかで、それにふさわしい関連性・意味を見出し、その対話を通じて自分を新しくして行く。このプロセスに身を任せてこそ、データは「情報」たりうるのだ。(『ドラッカーと論語』安冨歩 p.165)
情報からコミュニケーションを創出する
インターネットで「外の世界の情報」を得る目的は「学習」である。だから、大切なのはいかに多くの情報を得るかでも、いかに多くの情報を流すかでもない。目的と関連性とを明確にしてコミュニケーションを創出することにある。そのような本来の目的を見失ってしまうと、情報に基礎を置く組織を作ることができない。(略)すでに見てきたようにドラッカーは、情報とはデータに関連性と目的とを与えたものだ、と述べている。ということは、目的を見失った情報というのは、単なるデータの山にすぎない。データはいくら集めても、そこに意味はない。ただ、膨大な量に圧倒され、やがてはそのデータの海のなかで溺れてしまうだけだ。(『ドラッカーと論語』安冨歩 p.181)
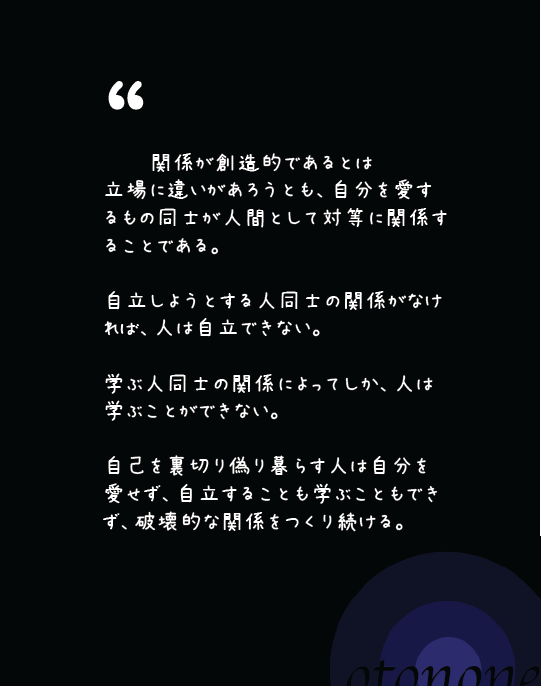
コミュニケーションが人格をつくる
「コミュニケーション」以前の「コミュニケーション」
「わたくし」に事前に意図があり、それがなんらかの行為へと変換されて「あなた」に渡され、それを「あなた」が解釈する、というコミュニケーション像は不十分である。まず場があり、そこに行為が生成されると同時に意図と解釈が生まれ、三点セット(意図・行為・解釈)が成立してコミュニケーションが実現し、それが場を再生産する。常にすでに動いてし合っている、ということがコミュニケーションを成立させるために必要なのである。
そしてさらには、意図と解釈の生成とともに、「わたくし」と「あなた」も生成していることに注意せねばならない。別にこれは奇怪なことではない。「わたしく」がこの世界に生まれ落ちたとき、「わたくし」はわけのわからない音声を発して、手足を不規則に蠢かせる生き物であった。その音声や動きから糸を解釈し、呼びかける人々の思いによってそこに場が形成され、そのなかで「わたくし」はコミュニケーションの技芸をみにつけていったのである。生まれ落ちた瞬間から、死に至るその瞬間まで、私たちはこの運命から逃れることはできない。成長とはまさしくコミュニケーションの場の生成を通じて人格を育てる過程にほかならない。どのようなコミュニケーションと場に置かれるかによって、人格は大きな影響を受ける。それは当たり前のことである。(『複雑さを生きる』安冨歩 p.65)
「同期」
スピノザがホイヘンスの驚くべき同期実験を知っていたとすれば、その思想的意味をそこから汲み取らなかったと考える方が不自然である。そしてスピノザの思想は、このホイヘンスの実験と整合している。それは実験に由来する、というよりもむしろ、スピノザがもともと抱いていた思想が、ホイヘンスの実験と整合していた、と考えるべきであろう。ここでは、ホイヘンスの実験を念頭に置くことで、スピノザの南海とされる諸概念が、わかりやすいものになることを示す。たとえば、第二部補助定理三のなかの公理二の定義は次のようになっている。(略)
定義 同じあるいは異なった大きさのいくつかの物体が、他の書物体から圧力を受けて、相互に接合するようにされている時、あるいは(これはそれらいくつかの物体が同じあるいは異なった速度で運動する場合である)自己の運動をある一定の割合で相互に伝達するようにされている時、我々はそれらの物体がたがいに合一していると言い、またすべてが一緒になって一物体あるいは一個体を組織していると言う。(『合理的な神秘主義』安冨歩 p.98)
このとき問題になるのは、接続されているシステムの全体である。その構成要素の形や性質のみならず、接続関係のあり方が、安定状態を決定している。たとえば二つの柱時計の距離が離れすぎると、もはや一つのシステムとしては作動しなくなり、それぞれの元来の振動数を刻むことになる。あるいは、柱時計が接続されていても、接続素材や柱時計の性質の組み合わせによっては、動悸が起きないケースもある。たとえばホイヘンスの実験では、柱時計が互いに向き合うように設置した場合には、同期が起きなかった。この観点から「歴史認識問題」を見れば、共通の歴史認識を無理に作っても意味がないことは明らかである。それぞれの社会が違った作動をしているなら、無理にそのような共通認識を作り出しても、やがてまた分離してしまう。大切なことは、双方が接続されており、一つのシステムとして作動することである。そうすると、それぞれの認識は「正反対」となりながら、なんらかの「共感」を見せて、全体としては安定した状態を作り出すかもしれない。そもそも「歴史認識問題」という形で、ときおり騒ぎが起きて、ゴタゴタしていること自体が、ホイヘンスの椅子がガタガタしたように、安定化作用の表現かもしれないのである。そこを無理に調整すると、安定状態が損なわれてしまいかねない。対話によって、互いの考えをぶつけあうことで、二つの柱時計の接続を維持し、その対話を通じて、それぞれに考えを発展させていけば、全体としての安定は失われないであろう。注意すべきは、自分の「考え」なるものを他人に押し付けて対話を封じ込める態度であり、そのようなものを許してはならない。(略)双方が互いに相手のメッセージを受け止め、それぞれが学習することがコミュニケーションの本義であることを忘れてはならない。いうまでもないが、これは「歴史認識問題」に限定されることではない。何か紛争があると、そこに「共通の何か」がかけているのが原因だと考えて、「合意」「協定」「共通認識」「共通理念」「共通の目的」「共通の伝統」「共通の歴史」等々を作り出して問題を解決しようとするが、それは危険なことである。(『経済学の船出』安冨歩 p.226)
椅子と柱時計と板とで構成されたシステムの振り子の同期を乱した瞬間に、椅子がガタガタ言い出したら、現代人でも仰天するのではあるまいか。少なくとも私は、事前に知っていてもギョッとすると思う。ストロガッツも、
ホイヘンスは、振子の「共感」を崩したら何が起こるか試してみた。この実験結果には、ホイヘンスも度肝を抜かれたに違いない。というのも、板を渡した椅子が振動しはじめたからだえる。時計が「共感」している間は動きを見せなかった椅子は今や床の上で震え、ざわついていた。
(『経済学の船出』安冨歩 p.234)
「同期=秩序」とか「同期=調和」と考えるわけにはいかないのである。(略)ヒトラーやスターリンや毛沢東といった人物は、人間を同期させるのがうまかった。アジア太平洋戦争に突入する過程の日本社会でも、強烈な動悸が、それも確たる指導者なしに形成されていた。あるいはバブルの発生とその崩壊という、社会に大きな被害を与える経済現象も、また同期の結果である。同期現象への注目は、コムニスの認識障害からの離脱には有効であるが、新たな認識障害を引き起こす可能性をもっていることを忘れてはならない。(『経済学の船出』安冨歩 p.236)
この場合、椅子と梁と時計をそれぞれに調べても何もわかりません。つまり、対象を要素に分けてどんなに分析しても、「同期」という現象は出てきません。椅子と梁と時計が作り出す繋がりを、一つの関係と見て取り出すということが必要です。その全体が「同期」という現象を引き起こすのです。あるいは逆に、「同期」という現象が、その「全体」を確定します。そういう発想で世界を眺めた場合、人間というものがどのように見えるかと言うと、人間と鳥と虫と草花などとの関係において眺めるわけですから、人間を調べ、鳥を調べ、むしろ調べるというやり方では、何も見えてきません。そうではなく、それぞれのつながりを調べようということになったはずです。それを三百五十年前にやっていれば、今頃私たちはもっと賢かったと思うのです。私のやろうとしているのは、世界をばらばらにするやり方ではなく、繋がりを調べるやり方に変えていこうではないかということになるのです。しかし、考えてみれば、繋がりとして世界を見る見方は、二千五百年くらい前からすでに存在しているわけです。「縁起」という考え方です。(『生きるための親鸞』安冨歩・本多雅人 p.138)
破壊的構えと創造的構え
他人に押し付けをする、というのは、どういう心持なのか、少し考えてみましょう。人は、自分が受けいられれる経験をすると、人を受け入れることができるようになります。これに対して、自分が受け入れられず、なんらかの像を押し付けられた経験をすると、人にも同じことをしてしまうのです。特にこれは、子供の頃の経験が大きな意味を持ちます。なぜなら、子供の時の体験によって、人は生きる上での基本的な「構え」を獲得するからです。一部の人は、子供のときに受け入れられた経験のみを持っています。逆に一部の人は、そのような経験を全く欠いています。大抵の人は、両方の経験を持っています。
受け入れられた経験のみを持つ人は、他人に対して像を押し付けることはしません。また、そういうことをされたら、強い不快感を感じて、それを表明し、受け入れられないなら、その場を去ります。このような構えを「創造的構え」と呼ぶことにします。というのも、双方が互いに人間として尊重しあって胃rばにおいて、人間は創造性を発揮するからです。(略)逆に受け入れられた経験を持たない人は、他人に対して像を押し付ける以外の方法を知りません。このような人は、出会った人の実像をありのままに捉えるのではなく、その人を自分が勝手に用意した分類表のどこかに適当に押し込めて、理解したことにしてしまいます。そして、自分に都合の良い像を他人に押し付け合うことこそが、人間関係の本質だ、と考えています。このような構えを「破壊的構え」と呼ぶことにします。「破壊的構え」の人は、「創造的構え」の人よりもよく目につきます。というのも、こういう人が社会的な「成功」を収めやすいからです。会社や役所や大学といった組織でも、権力を握っている人には、こういうタイプが多いのです。その最大の特徴は、自分より弱い人を躊躇なく攻撃することと、自分より権力を持つものに、これまた躊躇なく媚びへつらうことです。彼らがこういうことに躊躇しないのは、人間とはそういうものだと思い込んでいるからです。
両方の経験を持つ人は、両方のモードを持っているので、常に両者がせめぎ合い葛藤して、どうしてよいかわからなくなります。それゆえ、周囲の流れに流されてしまいがちです。これを「葛藤の構え」と呼びましょう。(『生きる技法』安冨歩 p.44)
破壊的構えの人が「上司」になることが多いのは、その組織が「破壊的構え」によって成り立っているからである。
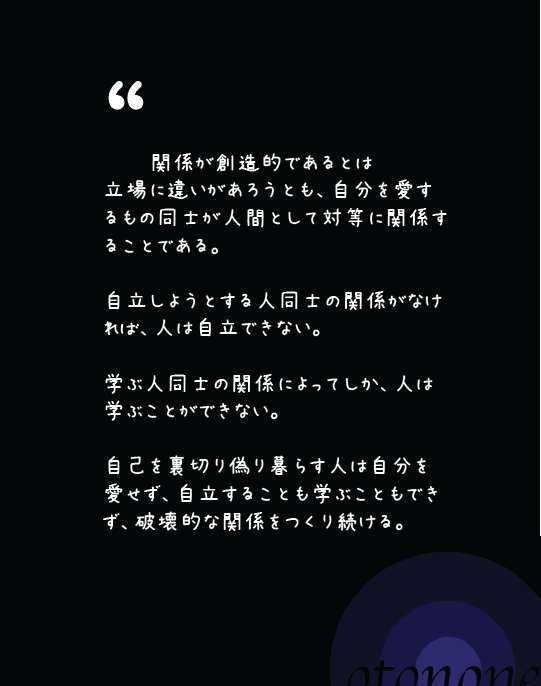




コメント